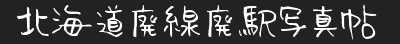
白糠線
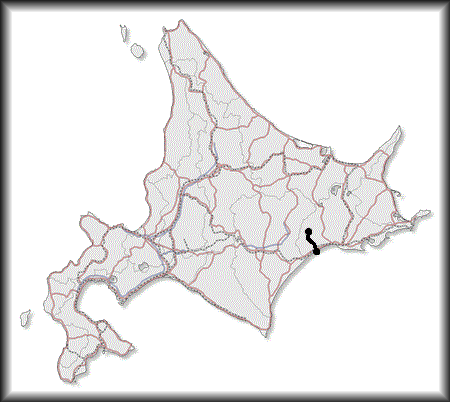
白糠線(しらぬかせん)は、日本国有鉄道(国鉄)が運営していた鉄道路線(地方交通線)である。
北海道白糠郡白糠町に所在する根室本線白糠駅から分岐し、同町二股地区の北進駅までを結んでいた。
沿線の石炭及び森林資源の開発を目的に計画された路線で、本来は、改正鉄道敷設法別表第147号の2に規定する予定線として池北線の足寄駅に結ばれ、
さらに足寄駅から新得駅までの北十勝線(未成線)とあわせて根室本線のバイパスを形成するはずであった。
1964年に上茶路駅までが開業し、釧路二股駅までの工事も日本鉄道建設公団の手により1970年には完成していたものの、
折しも「赤字83線」のローカル線廃止取組みの最中であり、開業すれば赤字必至のローカル線の引き受けを国鉄が拒否したため、
釧路二股駅までの開業はこの取組みが頓挫した1972年に当時の運輸大臣であった佐々木秀世の命令という異例の形で行われた。
その際、延長区間に2駅設置された奥茶路駅と終点である釧路二股駅に関してはさらなる延長への期待を込めて延長開業時にそれぞれ「下北進」および「北進」と変更されている。
しかし、沿線の炭鉱(雄別鉄道上茶路坑)は1970年にはすべて閉山し、人口が激減。手を組むはずであった北十勝線も頓挫し、
1980年に国鉄再建法が成立すると、白糠線は第1次特定地方交通線に指定された。
この時白糠線は営業係数3,077(100円稼ぐのに3,077円かかる)という国鉄一の赤字状況であり、代替道路の状況等、廃止への条件が整っていたため、
特定地方交通線の先陣を切って1983年に廃止された。開業から19年、上茶路 - 北進間が延伸開業してわずか11年後だった。
『フリー百科事典 ウィキペディア日本語版』より(一部加工)
白糠駅へ